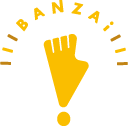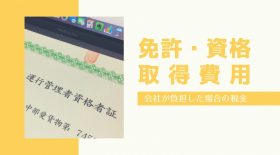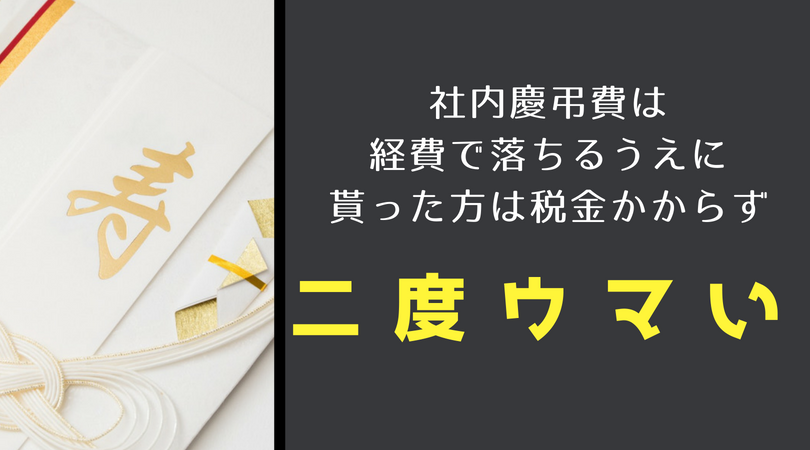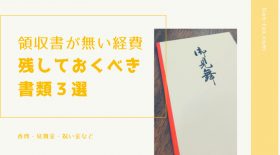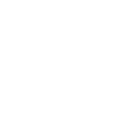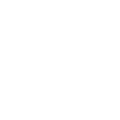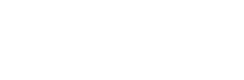税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。
帰宅困難者対策用品を購入したんだけど、経理処理はどうしたらいいの?
そうお考えの方へ向けた記事です
当記事では、帰宅困難者支援セットなどの災害用備蓄品購入時の経理会計処理について解説しています。
読んでいただくと、次のことが分かりますよ!
災害用備蓄品について
- 勘定科目は何にすればいい?
消耗品費で処理します - 経費にするタイミングは?
備蓄開始時点で全額経費にします - 消費税の処理はどうすればいい?
飲食料品については軽減税率、その他は標準税率が適用されます
勘定科目は消耗品費
災害用備蓄品は、「消耗品費」という勘定科目で会計処理します。
「消耗品費」は、繰り返し使用しないものをあらわす勘定科目だからです。
なお繰り返し使える備品であっても、1個あたり10万円未満のものについては、同様にこの勘定科目で処理します。
繰り返し使える備蓄品で1個10万円を超えるもの(そんなものあるのでしょうか?)については、「工具器具備品」などの勘定科目で計上したうえで、減価償却します。
備蓄開始時点で経費にする
災害用の備蓄品は、備蓄を開始した時点で全額経費にします。
消耗品は通常、使用してはじめて経費にします。
未使用分ついては、使用するまでは在庫(「貯蔵品」という勘定科目)として計上しなければいけないのです。
いっぽう災害用備蓄品は、備蓄することを目的として購入するものです。
「使用しないに越したことはない」というものですよね。
ですから、使用したときにはじめて経費にするという考え方が馴染みません。
したがって、備蓄を開始した時点で、購入金額の全額を経費として計上するのです。
繰り返し使える備蓄品で1個10万円を超えるものについては、実際に使用していなくても備蓄開始時点から減価償却します。
飲食料品は消費税軽減税率
災害用備蓄品のうち、飲食料品については軽減税率が適用されます。
酒、外食を除く飲食料品は、それが備蓄を目的としたものであっても軽減税率の対象となるためです。
いっぽう、手回しランタンや毛布などの備品は飲食料品ではありませ。
したがって、標準税率(10%)が適用されます。
まとめ
災害用備蓄品の経理会計処理について解説しました。
災害用備蓄品について
- 勘定科目は何にすればいい?
消耗品費で処理します - 経費にするタイミングは?
備蓄開始時点で全額経費にします - 消費税の処理はどうすればいい?
飲食料品については軽減税率、その他は標準税率が適用されます
この記事を書いたひと

- 税理士
-
税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
記事執筆・監修実績はこちら。
最新記事一覧
- 2024年6月14日-税理士業のこと経理職への転職に関する記事を監修しました
- 2024年4月22日-税理士業のこと所得税と住民税の税務記事を監修しました
- 2024年1月22日-税理士業のことフリーランス美容師向け税務記事を監修しました
- 2023年10月31日-税理士業のことバーチャルオフィスに関する記事を監修しました